定額減税補足給付金(不足額給付)について
制度概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族等一人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
また、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、定額減税しきれない額を「調整給付金(当初給付分)」として令和6年度に支給しました。この給付は、できるだけ早期に給付するため、令和5年分所得税額により令和6年分所得税額を推計して給付額が算定されました。
「不足額給付」とは、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、調整給付金(当初給付分)の支給額に不足が生じる場合などに、追加で給付を行うものです。

関連リンク
内閣官房ホームページ 「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイト)
総務省ホームページ 「個人住民税における定額減税について」(外部サイト)
対象者
令和7年1月1日時点で都留市に住所がある方で、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかの要件に該当する方。
(注記1)所得税・住民税合わせて既に一人あたり4万円の定額減税を受けられている方や、合計所得金額1805万円超えの方は、対象外となります。
(注記2)事務処理基準日(令和7年6月2日)時点で市が把握している情報を基に算定しています。
不足額給付1
調整給付金を再算定した結果、当初給付した調整給付金の額に不足が生じた方に対して、その差額を支給するものです。
令和6年度に実施した当初調整給付では、令和5年所得等を基にした推計額を用いて給付額が算定されました。
そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに給付額を再算定した結果、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じる場合があります。
当初調整給付額に不足が生じた方に、その差額を1万円単位で切り上げて支給します。
(注記)再算定した結果の調整給付金にあたる額を当初調整給付において既に受け取っている場合、不足額給付の対象とはなりません。
対象となりうる例
令和6年中に扶養親族が増えた方
「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった場合
(注記1)所得税分定額減税可能額とは、本人及び扶養親族等一人につき3万円です。
(注記2)個人住民税の定額減税額は令和5年12月31日の状況で判定するため、この場合でも住民税定額減税額は変わりません。

令和5年所得に比べて、令和6年所得が減少した方
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった場合

不足額給付2
本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対して、一人あたり原則4万円を支給するものです。
(注記)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。
(注記)「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」 に該当の場合、1万円〜3万円の個別の給付額となります。
以下のいずれの要件も満たす方が対象です。
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(≒本人として定額減税対象外)
- 税制度上、「扶養親族等」に該当しない(≒扶養親族としても定額減税対象外)
- 低所得世帯向け給付の対象世帯主・世帯員に該当しない
(注記)「低所得世帯向け給付」とは、次の給付です。
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
また上記のほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する場合は、対象となる場合があります。 「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」とは、低所得世帯向け給付の対象世帯主・世帯員に該当しない者で次のいずれかに該当する場合です。
- 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税から外れてしまった場合
- 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
- 令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
対象となりうる例
課税世帯に属する事業専従者
同じ世帯にいる所得税・住民税所得割課税者である個人事業主の専従者であって、自身は所得税・住民税所得割ともに非課税の場合

課税世帯に属する合計所得金額48万円超えの方のうち、令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割が0円の方
合計所得金額が48万円を超えているが、所得控除や本人の状況(障害者控除の適用を受けるなど)により所得税・住民税所得割ともに非課税で、また世帯内に納税者がいるため低所得世帯向け給付の対象にもならなかった場合

申請方法
不足額給付1に該当する方
1.市役所で口座情報を把握できた方
8月4日(月曜日)に、支給額および支給日を記載した「支給のお知らせ」を発送しました。
不足額給付1に該当する方のうち、令和6年度に当初調整給付金を受け取っている方や、マイナンバーカードを利用した公金受取口座を設定している方などが対象です。
「支給のお知らせ」が届いた方は、原則として申請等の手続きは必要ありません。
振込先口座を変更する方や受給を辞退される方は、8月25日(月曜日)までに申し出てください。
支給予定日
令和7年9月10日(水曜日)
2.市役所で口座情報を把握できていない方
8月4日(月曜日)に、支給額が記載された「支給確認書」を発送しました。
不足額給付1に該当する方のうち、市役所で口座情報を把握できなかった方が対象です。
「支給確認書」が届いた方は、口座情報など必要事項を記入し必要書類を同封のうえ、10月31日(金曜日)までに市役所へ返送してください。
市で書類受付後、内容を確認のうえ順次支給予定です。
【訂正】お送りした支給確認書には、本人確認書類および口座確認書類を「本人確認書類等貼付用紙に添付」するよう記載がありますが、これは記載誤りです。「本人確認書類等貼付用紙」は送付していませんので、必要書類は貼らずに同封していただくようお願いします。訂正しお詫び申し上げます。
必要な書類
- 支給確認書
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)のコピー
- 振込先口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)のコピー
令和6年1月2日以降に都留市へ転入された方のうち、不足額給付1に該当する方
令和6年1月2日以降に都留市へ転入された方のうち、不足額給付1に該当すると思われる方は申請が必要です。
令和6年1月1日時点で都留市以外にお住まいだった方は、都留市に令和6年度住民税情報等がないため給付の対象となるか判断できませんので、申請が必要です。
申請が必要な方
令和6年1月2日以降に都留市に転入され、令和7年1月1日時点で都留市に住所がある方のうち、「令和6年分所得税および定額減税の実績額で算出した調整給付額」が「当初調整給付額(令和6年度に実施)」よりも多くなった方
申請方法
詳細については、前年の給付実績がわかる資料(調整給付金支給通知書など)または令和6年度個人住民税の税額通知書などを用意し、10月31日(金曜日)までに税務課市民税担当へお問い合わせください。(注記:期限を延長しました)
(注記)前年の給付実績がわかる資料などを用意できない場合は、都留市から前住所地の自治体へ照会し必要な情報を取得するため、支給までに時間を要します。
不足額給付2に該当する方
都留市で把握できる範囲で、不足額給付2に該当すると思われる方には、9月1日(月曜日)に「申請書」を送付しました。
「申請書」が届いた方は、口座情報など必要事項を記入し必要書類を同封のうえ、10月31日(金曜日)までに市役所へ返送してください。
必要な書類
- 申請書
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)のコピー
- 振込先口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)のコピー
(注記)公金受取口座への振込を希望する場合、通帳やキャッシュカードのコピーは不要です。
令和6年1月2日以降に都留市へ転入された方のうち、不足額給付2に該当する方
令和6年1月2日以降に都留市へ転入された方のうち、不足額給付2に該当すると思われる方は申請が必要です。
令和6年1月1日時点で都留市以外にお住まいだった方は、都留市に令和6年度住民税情報等がないため給付の対象となるか判断できませんので、申請が必要です。
申請方法など詳細については、10月31日(金曜日)までに税務課市民税担当へお問い合わせください。(注記:期限を延長しました)
不足額給付2のうち「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する方
不足額給付2のうち「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当すると思われる方は、申請が必要です。
事前に市で把握することが困難なため、ご本人からの申請が必要です。
申請方法など詳細については、10月31日(金曜日)までに税務課市民税担当へお問い合わせください。
不足額給付の対象になると思われるが、市役所から通知が届かない方へ
市で対象者として把握できない場合もありますので、不足額給付の対象者に該当すると思われた方は、10月31日(金曜日)までに税務課市民税担当へお問い合わせください。(注記:期限を延長しました)
定額減税給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
不審な電話や郵便、メールがあった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課市民税担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049
- このページへのご意見をお聞かせください
-
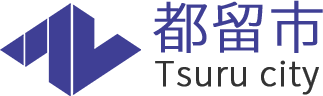
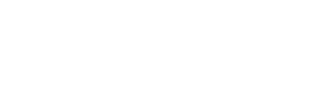

更新日:2025年09月24日