後期高齢者医療制度の保険料
被保険者一人ひとりに保険料が賦課されます。
保険料の決まり方
保険料は、おおむね2年間の医療給付費がまかなえるように、山梨県後期高齢者医療広域連合が定めた保険料率をもとに、被保険者全員が個人単位で納めます。
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計です。
被保険者の保険料(10円未満切捨て)={均等割額50,770円}+{所得割額(所得-43万円)×11.11%}
保険料率は山梨県後期高齢者医療広域連合によって決定され、2年ごとに見直されます。
令和6・7年度の保険料率は、団塊の世代の加入による被保険者数の増加、被保険者一人にかかる医療給付費の大幅な増加、医療給付費の一部を負担する74歳以下の人口減少、国の制度改正による「出産育児支援金」の導入などの要因によって、必要な範囲で増額改定されました。
また、山梨県内統一の保険料となっております。
なお、年収約1000万円を超える方を対象とする賦課限度額(保険料負担の年間上限額)の引き上げが段階的に実施され、令和6年度は年73万円が、令和7年度は80万円が上限になります。(ただし、令和6年度に75歳に到達する方はこの激変緩和措置の対象外となります。)
こんなときは保険料が軽減されます(所得が低い方の軽減措置)
均等割軽減
同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が下記の表に該当する世帯の被保険者は、均等割額が軽減されます。
| 軽減割合 | 判定方法 |
|---|---|
| 7割軽減 | 「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)」以下の世帯 |
| 5割軽減 | 「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)+30.5万円×被保険者数」以下の世帯 |
| 2割軽減 | 「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)+56万円×被保険者数」以下の世帯 |
- 「年金・給与所得者数」とは、同じ世帯にいる公的年金等の収入額が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円又は給与収入が55万円を超える被保険者及び世帯主の合計人数となります。
- 世帯は該当年度の保険料賦課基準日(4月1日)で判定しますが、年度途中に資格を取得した場合は、資格を取得する日で判定します。
- 公的年金を受給されている方は、年金所得からさらに15万円を控除した額で判定します。
- 世帯に所得が判明しない方(未申告者など)がいる場合は、軽減を受けられない場合があります。
職場の健康保険などの被扶養者だった方
後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険の被扶養者だった方は、後期高齢者医療制度に加入してから2年は均等割額が5割軽減されます。所得割額は課せられません。
また、世帯の所得が低い方はより高い軽減割合である7割軽減が適用される場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課保険年金担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622
- このページへのご意見をお聞かせください
-
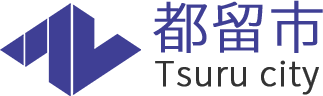
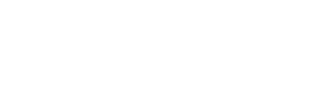

更新日:2025年05月13日